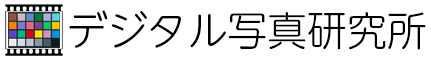FUJIFILM X-H2 を購入しました!
発売から1年が経過してしまいましたが、FUJIFILM X-H2 を購入しました。
風景写真を目的として、これまで FUJIFILM X-H1 を 6年ほど使ってきましたが、色々と検討した結果入れ替えすることにしました。入れ替えを決めた理由や、FIJIFILM X-T5 との比較検討内容やファーストインプレッションをシェアしたいと思います。
目次
FUJIFILM の Xシリーズを使う理由
第一に「フィルムシミュレーション」
特に「Vivid/Velvia」がお気に入りで、2002年から Canon のデジタルカメラで風景写真を撮影してきましたが、色の「こだわり」のため FIJIFILM に乗り換えたほどです。正直なところ Canon と比べるとアクセサリー類の豊富さなどトータルで考えると不便なところも多いのですが、それでもフィルムシミュレーションにこだわって FUJIFILM を使っています。
第二に「システムの総重量が軽い」
レッドバッチのレンズでそろえるとそれなりの重量にはなりますが、それでもフルサイズの高性能なレンズでそろえるよりもコンパクトで軽い。三脚を Gitzo に変えたことと、カメラを Xシリーズに変えたことで体力的に随分と楽になりました。
第三に「価格」
Canon のフルサイズで一式そろえた場合と比較すると高性能でありながら、安価に一式そろえることができます。趣味とはいえコストパフォーマンスは大事ですよね。
カメラを入れ替えようと思った理由
これは単に新しいカメラが欲しくなった。これに付きます(笑)
ですが、それでもいくつか上げると、
- 手振れ補正が 7.0段に進化
- X-H1 と比較して高感度の解像力が向上
- X-Trans CMOS 5 HR と X-Processor 5 による新しい絵作り
- AF 性能(ピント精度)
- カラークローム・エフェクトとカラークロームブルー
などがあげられます。
「手振れ補正が 7.0段に進化」
今回の売りの一つである 4000万画素については、過去に Canon EOS 5DsR を使っていたのでそれほど大きな理由にはなりませんでした。逆に手振れ写真の連発であまり良い印象が無かったため、高画素よりも手振れ補正機能の方が重要でした。
「X-H1 と比較して高感度の解像力が向上」
風景写真ではISO高感度を高くして撮影するケースもありますが、その時の解像力に不満を持っていました。このあたりの改善ができればと考えました。
「X-Trans CMOS 5 HR と X-Processor 5 による新しい絵作り」
新しいセンサーとプロセッサはとても興味がありました。ネットを見ていると第二世代や第三世代の方がシットリして良かったとか、第五世代の方が立体感があって良いなど、もう興味深々です。ただ、富士フィルムの開発者の話を聞くと色作りは変えてないとのこと。面白そう。
「AF 性能(ピント精度)」
私の目ではピントがつかみづらい場面も多く、ピントは AF まかせです。しかし X-H1 ではピントが思ったように合わないことが少なからず発生していたので、このあたりの改善を期待しました。
「カラークローム・エフェクトとカラークロームブルー」
最後にすでに数年前から実装されている「カラークローム・エフェクト」と「カラークロームブルー」ですが、この機能は X-H1 には実装されなかったので試してみたい。風景写真ではかなり使える機能なのではないかと思っています。
とまぁそんな理由で入れ替えました。
FUJIFILM X-T5 と比較して X-H2 にした理由
第一の理由は「モードダイヤル」であること
富士フィルムのカメラの特徴でもあるレトロなデザインと、独立したダイヤルの操作感はとても好きなのですが、絞り優先とシャッタースピード優先を切り替えることが多い私の撮影スタイルではちょっと面倒だなと感じていました。まぁ、Canon を長く使っていたせいもあるかも知れませんが。モードの切り替えや、設定の呼び出しが素早くできる点は大きいです。
具体例を上げると、シャッタースピードは「高速シャッター」と「スローシャッター」の設定を変える場合、時間をいちいちダイヤルで調整するのが面倒でした。また、絞り優先とシャッタースピード優先の切り替えも左上のダイヤル操作で切り替えられるのも良いです。(カスタムモードは7つまで登録可能で簡単に呼び出しができる)
第二の理由は「X-T5 はボディサイズが小さい」こと
私は手が大きく、レッドバッチのレンズを多用するので、グリップの小さい X-T5 は NG でした。また、バッテリーグリップが廃止されたことも大きかった。やはりグリップは重要です。
第三の理由は「シャッターフィーリング」
これまで使っていた X-H1 のシャッターボタンは、フェザータッチを売りにしていましたが、あまりにも軽すぎるため不用意にシャッターを切ることが発生していました。ですが、そのソフトなシャッターフィーリングは心地よく、とても気に入っていました。X-H2 はそのシャッターフィーリングをそのままに使いやすいシャッターボタンに改良されていました。
以上3点が主な理由です。
その他、小さなポイントとして
- 手に持ったときの質感
- ボディ天面のサブ液晶モニター
- フラッグシップ機という響き
があげられます。
「手に持ったときの質感」
某カメラ店にて両方の機種を手に取ったときに感じた「質感」です。塗装やカメラ上部の作り、手に持ったときの重量感などでしょうか。逆に軽量コンパクトなカメラを好まれる方は、X-T5 を選択されるでしょう。
「ボディ天面のサブ液晶モニター」
あと小さなことですが、ボディ天面のサブ液晶モニターは重宝します。撮影可能枚数やバッテリー残量がカメラの電源OFFでも確認できるのは良いですね。ただ、バッテリーは消費するでしょうけど。
「フラッグシップ機」という響き!
これはもうその言葉通りですが、気持ちの問題ですね(笑)
FUJIFILM X-H2 のファーストインプレッション
これまで使ってきた FUJIFILM X-H1 と比較して、どんなところが進化したのでしょうか。
違いを感じた点・良い点・気になった点などをまとめてみました。
違いを感じた点
- サイズはX-H1とそれほど変わらないが、最初に見たとき小さく感じた
- ビューファインダーの高さが低くなった
- 塗装の質感が変わった(マットでざらつき感がなくなった)
- バッテリーグリップの開閉レバーが自動的に戻らない(悪いわけではない)
- カメラの前面及び背面にあるコマンドダイヤルで、押し込んだときの操作が廃止になった
- フォーカスレバーの形状が変更になった
良いなと思った点
- 背面のリアコマンドダイヤルが回しやすくなった(親指の第一関節付近で回しているため)
- 本体のUSB充電でバッテリーグリップのバッテリーも充電できる(以前はバラバラだった)
- 本体取付時のロックダイヤルに突起がついて締めやすくなった
- 本体の底にある「縦位置バッテリーグリップ用端子カバー」が取り外しやすくなった
- USBモバイルバッテリーから給電できる
- ストラップ取付け用の金具?とリングがなくなり、手に当たらなくなった
- カスタムモードが7つまであり、絞りやシャッタースピードの設定を瞬時に切り替えられる
- リモートレリーズ端子が右側に移動し、L型プレートの縦位置撮影がしやすくなった
- シャッターボタンに遊びができ、操作がしやすくなった(X-H1 は慣れないと不要なシャッターを押してしまう)
- グリップ全体に厚みが増し、握りやすくなった
気になった点
- 露出補正ボタンが廃止
- バッテリーグリップを取り付けるときに本体の端子カバーを外すが、これをグリップ側で収納する場所がなくなった
- XF16-55 を付けたとき、グリップを握った手(指)が絞りリングにあたる
- フォーカスレバーの操作には慣れが必要?
購入後の感想
巷では X-T5 が人気ですが、なぜか X-H2 を酷評する人が多い。私は X-H2 の方が質感も高く購入して良かったと思っています。
ただ、アクセサリー関係は X-H2 用のものが少ないのが残念です。例えば、RRS (Really Right Stuff) の L型プレート。バッテリーグリップ用が無いのは仕方ないとしても、本体用もなくなった。これにより、クランプやプレートなどの見直しが発生。現在調査中となっています。
逆に、SONY のアルファ―シリーズだけ対応しているメーカーもあるくらいですから、その差は歴然。まぁ、仕方ない。
以上、購入後の感想でした。
これから購入される方の参考になれば幸いです。